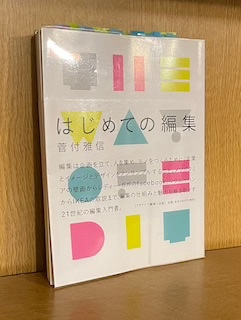
はじめての編集
菅付雅信
アルテスパブリッシング
かつての情報集積地だった教会から、ラジオ、新聞、週刊誌、広告など編集がおこなわれた歴史と変遷を、一気にながめることができる。そのポジションがいまやインターネットやグーグル検索が担っている。企画することはかけ算とよくいわれるが編集もまたしかりで、発想それ自体は変わらない。ただ編集にもひとつの法則、美しい決まりごとがあるという点で、「はじめての編集」は独特な主張がある。
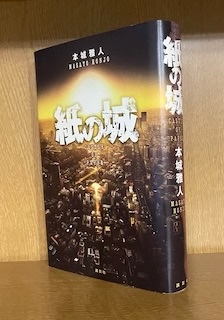
紙の城
本城雅人
講談社
IT会社が新聞社を買収しようとするところに、策謀と人間ドラマが展開される。テーマそのものが媒体の新旧が対決になっていて、その構図が示唆に富んでいる。と同時に、どうして新聞社がインターネットの覇権を握れなかったのか、その背景の一端がわかる。興味があるものを検索できるインターネットか、興味ないものでも広汎に知識が入ってくる新聞か。メディアのちがいは、哲学のちがいとなってあらわれる。
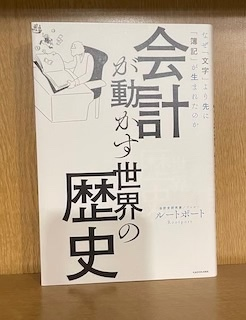
会計が動かす世界の歴史
ルートポート
株式会社KADOKAWA
簿記の貸方と借方のバランス概念が、群れのなかでうまくやっていく人間の種としての記憶からきている。そういった主張は、なかなか斬新だった。これだけにとどまらず、会計を軸に目をひく情報がずらりと並んでいる。専門家ではこうは書けない。主要なテーマは投資と経済発展だが、経済の歴史をあえて簿記でまとめたところがユニーク。
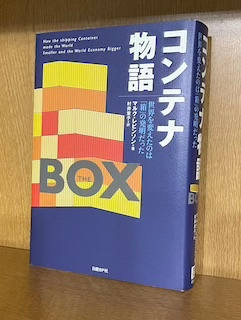
コンテナ物語
マルク・レビンソン
村井章子=訳
日経BP社
コンテナ船を発明したのが、じつはコンテナにまったく関係ない素人のトラック運送業者だったというのは驚き。たったひとつコンテナの規格を変えるだけで物流のありかたが変わるのだから、規格標準は侮れない。発明したのはビジネスモデルでも技術でもなくて、単なる箱なのだから。