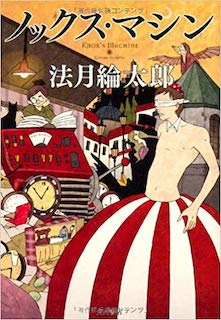
『ノックス・マシン』
法月綸太郎
角川書店
ヘイスティングス大尉は、とある手紙を受けとります。差出人は、引き立て役倶楽部会長のワトスン博士。そこにはA.Cが倶楽部との協定を反故にし、引き立て役を無に帰そうとしていると、A・Cを糾弾する内容が書かれていました。
”議事資料として、さる筋より入手した文書を同封する。今年の秋、コリンズ社から出版されるA・Cの新作の校正刷りだ。この原稿を読めば、彼女が十三年前にわが倶楽部と結んだ<協定>を反故にし、われわれの存在意義を無に帰そうとしていることが、貴君の目にも明らかになると思う。ゆゆしき事態が目前に迫っているのだ!”

ちなみにイニシャルでかかれているA・Cとはアガサ・クリスティのことです。もちろんここに出てくるワトスンはホームズの助手であり、ヘイスティング大尉はポアロの助手です。
謎の秘密結社
この一風変わった短編では、探偵小説の助手たちがあつまって秘密の会合をおこなっているという設定になっています。いわゆる職業組合とでもいうのでしょうか。とてもユニークな設定です。
ワトスンは、A・Cが引き立て役を排したの作品を書いたことに憤慨していて、
”クリスティ女史は作者と読者がじかに対峙する、新しいタイプの探偵小説を創造したといえよう。探偵とワトスンの一人二役を演じるのは、読者にほかならないのだから……。
同時にそれは、名探偵とその助手のパートナーシップを不動の礎とする<引き立て役倶楽部>への新たな宣戦布告でもあった。彼女の類まれな筆力と進取の精神は、われわれの存在が探偵小説にとって欠かせないものではなく、むしろ時代遅れの骨董品になりかけているということを、白日の下にさらしてしまったのである。”
といった内容が滔々とかたられ、引き立て役たちの会合がはじまります。
引き立て役の会合というのもユニークですが、会合では助手からみた推理小説評が語られていて、その内容が目をひきます。

たとえば、
”われわれを排除しようとする勢力のことだよ、ヘイスティング君! 昔はよかった。名探偵の活躍は、必ず無二の親友の手記を通して、読者の許へ届けられたものだ。超人的な頭脳の持ち主には、彼と行動を共にする常識人のパートナー、すなわち読者が共感できる語り手が欠かせない。孤立したむき出しの知性ほど、味気ないものはないからだ。
わしはデュパンの友人のような引き立て役が間に入るからこそ、読者は不可解な謎に頭を悩ませ、名探偵の披露する驚くべき推理に心から喝采を送ることができる。それがどうだ。近頃の連中ときたら、ワトスン方式は古臭い、時代遅れいだなどと抜かして、探偵小説の世界からわれわれの影響力を一掃しようと躍起になっている。”
と引き立て役が、みずからの役割を解説するというメタぶりです。
水戸黄門でいうなら、普段おちゃらけているうっかり八兵衛が、まじめな顔で解説するようなものです。身もふたもないとはまさにこのことです。■エラリー・クイーンも餌食に
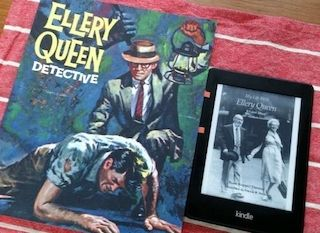
また作中では、エラリー・クイーンをひきあいに出して、
”引き立て役の伝統に忠実なふりをして、われわれの目を欺くために。倶楽部からの抗議に対して、クイーンは平気な顔で、ワトスン役をないがしろにしたことはない、父親のクイーン警視がその役目を果たしている、とうそぶきました。しかし、肝心のクイーン警視は、公職に就いていることを理由に、倶楽部への入会を拒絶したのです……。やつらの魂胆は明らかだ。由緒ある引き立て役の存在を消し去って、愚鈍なアメリカの大衆にすり寄ろうとしている! あれでは、ハードボイルド派の連中と選ぶところがない”
と述べています。
助手の使い方を解説してパロディに仕立てようだなんて、狙いがニッチすぎます。どんだけマニア向けなんだと。「この本の狙ってる読者層って、どのへんですかね?」とそのことを考えずにはいられません。
本格とパロディの間
法水倫太郎でよんだことがあるのは、「生首に聞いてみろ」やら「雪密室」です。わりと本格推理──というか、こてこての本格推理モノです。
本格推理ということもあり、法水作品は一本筋のとおった無骨なイメージがします。遊びが少なく、古典的なトリックをとりこんだ作品といえばいいでしょうか。たとえていうなら、ひとつの様式にのっとってつくられた完成された建築をおもいおこさせます。

その法水倫太郎が、くだけた作風のパロディを書くのですから、驚きもひとしおです。しかもユーモアと皮肉のバランスが絶妙で、あっちでこけおろしこっちで持ち上げては、見事に笑いをとります。
しかしパロディとはいえ、これまた本格推理に根ざしたパロディであることも事実です。配役は助手で、問題となっているのも探偵小説、しかもこきおろすのもアガサクリスティーですから、本格推理の要素がふんだんに盛りこまれています。これは堪りませんね。
どこまでいっても本格推理。
法水倫太郎はブレません。