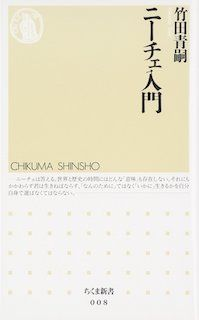
『ニーチェ入門』
竹田青嗣
ちくま新書
哲学を読むときは、専ら、竹田青嗣先生の本を手にとることが多いです。今回は、その竹田先生が著した「ニーチェ入門」。ニーチェが専門というわけでもないのに、とてもわかりやすい内容になっています。
なぜ、竹田先生の説明は、かくもわかりやすいのか?
ひとつは、時代背景がしっかりしているところです。哲学の説明のなかになんらかの時代背景があると、当時の社会ニーズとニーチェの主張を比較することができます。たとえば、社会はこういう風潮だったがニーチェは別のことを考えていたとか、ニーチェのこういうところが革新的だったとか、ニーチェがなにを問題にしていたのかよくわかります。
そのため、ニーチェの主張を端的に理解するうえで、当時の時代背景は欠かせないといえます。
人気者ニーチェ
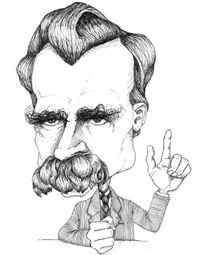
ニーチェは、二〇世紀の思想の源泉として、クローズ・アップされつづけています。というのも、ニーチェ復権のうらには、マルクスの衰退が関係しているからです。
では、対マルクスの関係でみた場合、ニーチェはどうなるでしょう?
それは、
”さて、ニーチェである。なぜニーチェは、「ポスト・マルクス主義」の位置を占める二〇世紀の新思想の源泉としてクローズ・アップされるにいたったか。
国家の死滅を叫び、国家権力を解体しようとして現れたマルクス主義思想が、自ら巨大な権力国家を作り上げてしまったこと。この事実はいわば二〇世紀ヨーロッパ思想最大のトラウマとなった。だから、資本主義の国家権力だけではなくむしろ権力一般を解体するような思想を見いだすこと、これがポスト・モダニズム思想の重要な課題となった。そしてニーチェの思想は、まさしくこの課題に強力な根拠を与えるものとして蘇ったのだ。つまり、ここでニーチェの思想は、なにより「権力的なもの」、「権力を作り上げる力学」に対する強力なアンチ・テーゼとして読み直されたのである。”
ということになります。
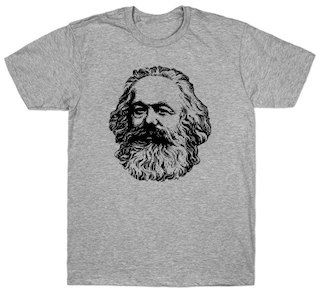
これを読めば、ニーチェが、マルクス主義の反動をなしているのがわかります。もっと砕けていうと、ニーチェはその強力なアンチテーゼによってもてはやされ、その人気ぶりは芸能界でいう嵐みたいな存在となっています。
あんな根暗で嫌味っぽい男が、嵐ですよ!
道徳批判
もうひとつは、竹田先生の論の展開が、きわめてわかりやすいところにあります。
ニーチェの代表的な考えとして、「ルサンチマン」があります。

ルサンチマンは、人間の恨み、妬みといった負の感情が循環している状態をいいます。ルサンチマンだけを見てると、ニーチェの云わんとするところがぼやけて、なかなか理解できません。理解できるにはできるのですが、だからナニ? みたいなもやもやが残ります。
しかし、ルサンチマンと道徳批判をならべると、これらの主張が対比され、すこし理解しやすくなります。
”道徳は出来そこない者どもが、ニヒリズムにおちいらないようにふせぐが、それは、道徳が、各人に無限の価値を、形而上学的価値をあたえ、この世の権力や階序のそれとはそぐわない或る秩序のうちへと組みいれることによってである。”
”道徳の起源は恐怖や不安にある。だから、道徳は群れ集まろうとする本能に由来する。またそういう意味で道徳は”弱さ”の現れである。道徳の代表的な徳目は「利他性」だが、これは弱者から出てくる。したがって道徳の基礎には願望がある……。”
”だから、ニーチェのこういう道徳批判を見て強い反発をもつ人々も多いに違いない。しかし、すでに見たように彼の道徳批判の最大の眼目は、道徳が人間の自然な生のありようを強く抑圧するにいたる、その奇妙な顛倒の理論を徹底的にあばくことにある。”

ルサンチマンが人間の弱さにとらわれた状態だとするなら、道徳はそれに陥らないようにする行為であり、その意味において道徳は望ましい姿であるといえます。しかしニーチェからすると道徳は、人間の弱さをあつめ、特定の者にとって都合のいいものに変えようとするある種の魂胆となります。自分の弱さにおちいったルサンチマンも最悪ですが、それをあつめて利用しようとする道徳はもっとも忌避すべきものなのです。
そういった偽善的な道徳を打破するために、道徳は、人間の生を不自然なかたちで抑圧していると、ニーチェはあからさまに批判しています。道徳批判は、一見すると狂人の理論ですが、人間の弱さに着目し、そこから脱却するために考えぬいた思考という点では、終始一貫しています。そして、ルサンチマンと道徳批判は、ある意味で、おなじ視線にたった考えといえるのです。
アンチキリスト
ニーチェは、道徳を、人間の自然な生のありようを抑圧しているとして批判します。大衆の反発をおそれない堂々たる物いいは、実にロックです。そして、もうひとつのニーチェ特有のロックな主張があります。それがアンチキリストです。

”「汝の敵を愛せよ」というキリスト教の教えは何を意味しているか。せんじつめて言えばそれは、「自分のために何かをしてはならない、ただ他人のためにだけ何かをなせ」という命令を意味する。そしてニーチェによればここにはある根本的な顛倒が存在する。「まず自分のために努力する。そしてつぎに、その余裕と力があるとき人は他人を助ける」、ということが人間の道徳的”自然性”だとすると、キリスト教はこれをまったく逆転しているからである。”
”「道徳」それ自体としては人間社会に必要不可欠なものである。しかし、それはある場合徐々に”うさんくさい”ものになり、また徐々に”危険なもの”になる。どういう場合には。「ルサンチマン」によって道徳の”自然性”が反転し、内向し、そして現世を超えたある「絶対性」と結びつくときである。そうニーチェはいう。”
ニーチェがキリスト教を批判するのは、道徳批判とおなじ理由です。ニーチェは、宗教を介した人間をながめつつ、そこに自然に反した要請を見てとっています。そして不自然な要請が、絶対的な真理となったとき、とても危険なものになると危惧しています。
よくいえば、彼は大衆のなかに自然発生するうさんくささに機敏に反応し、警鐘を鳴らしているのです。とはいえ、いささか鳴らしすぎではあるのですが。
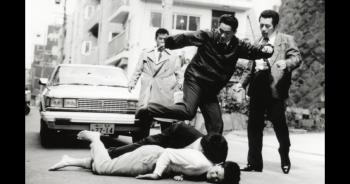
道徳批判であれ、アンチキリストであれ、ある種の真理が設定され、そこから絶対性が生まれ、絶対性によってうさんくささが糊塗されるのを、ニーチェはきらいます。そこに弱さにつけこんだ権力構造と支配欲の顕れをみつけるのです。
「ニーチェ入門」をよむと、ルサンチマンから道徳批判への展開が理解でき、道徳批判とアンチキリストのつながりもよくわかります。竹田先生の本がことさらよみやすいのは、こういった論点同士のつながりをふまえ、より深い理解が得られるからだとおもいます。