作中に骨がでてくると、異様な雰囲気がただよう。不気味さ、凶事、禁忌──。骨にはある種の不吉さがつきまとう。しかしこうやって作品を並べてみると、その印象もいくぶん変わる。一口に骨といっても、いろんな切り口がある。

狂骨の夢
京極夏彦
講談社ノベルス
妻の朱美の手にかかり、作家の宇田川が惨殺されるという事件がおこる。猟奇的な殺人事件で世間は持ちきりとなる一方、その裏で骨を求める修験者たちが暗躍していた。曖昧模糊とした記憶と、骨にまつわる謎、漆黒から現れた陰陽師が事件の全貌を解きあかす。
事件からテーマ、舞台設定まで、そのすべてが骨で埋めつくされている。執拗なまでに骨で統一されている。

浮遊封館
門前典之
原書房
タイトルをみたときは館系の話とおもったが、その予想はあっけなく裏切られる。飛行機墜落事故にあやしげな宗教団体がからんで事件は錯綜し、終盤に息をのむような凄惨な事実が明らかになる。死体や骨がでてくる話は数多くあれど、ここまで大量の骨が登場するのは珍しい。
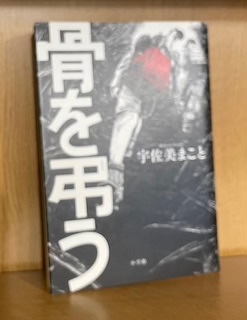
骨を弔う
宇佐美まこと
小学館
主人公は、小学生のとき学校の人骨標本を盗みだすいたずらをしていた。ふとしたことでいたずらの記憶がよみがえり「あれは本物の骨だったのではないか?」とおもいはじめる。かつての友人を訪ね人骨標本について質問をするが、現実生活に直面している友人たちはそれどころではない。人骨標本を盗みだした思い出ははるか彼方に追いやられ、やるせない現実に振りまわされる。かつて盗みだした人骨は標本だったのか、それとも本物だったのか。そもそもなぜ人骨標本を盗むことになったのか。各パートを読みすすむごとに、「骨」にまつわる冒険がかたちを変えていく。

風はずっと吹いている
長崎尚志
小学館
広島郊外の山中で、白骨遺体が見つかるところからはじまり、事件の記憶は原爆投下直後の広島へと連なっていく。とくに敗戦直後の生活風景は過酷で想像を絶する。生活の糧を得るために人骨を売るなんて考えただけでおぞましい。そんな阿漕な商売なんざ、羅生門の老婆だってしないだろう。