
『失われた過去と未来の犯罪』
小林泰三
角川書店
ある日、世界は「大忘却」とよばれる現象に見舞われます。
人類は、十数分前の記憶をうしなってパニックとなります。そして数分から十数後には、最初のパニックの記憶も消え、また新たなパニックがおこります。なぞの健忘症によって、人々は大混乱におちいるのでした。
その後、人工的に長期記憶をおこなう装置を完成させ、人類は大忘却を克服。記憶装置の小型化がすすむと、人々は身体にソケットを設置し、そこにメモリーを挿しこんで生活するようになります。
記憶の入れ替え

人類の記憶保持に役立ったメモリでしたが、この記憶装置が原因で厄介な事件が起こります。
たとえば大学生の双子陽菜と陽香は、メモリーの欠陥品を取り換えに行ったところ、作業員のミスで、同一の記憶を二つコピーしてメモリをもどされます。その日以降、双子はおなじ記憶から別々の記憶が派生することとなり、ひとりはAの身体におけるAの記憶として、もうひとりはBの身体におけるAの記憶として生活をはじめます。
また、お見合いをするはずだった男性が、駅で女性とぶつかり、階段からおちた衝撃でメモリが抜け落ちます。ふたりはメモリを入れちがいに挿入したまま立ち去り、そのあとお見合いの場で再会します。するとすでに記憶を共有したふたりは、話し合った末に「わたしたち、互いの一番深い秘密を知っている仲じゃないですか。だったら、もう結婚してしまうのはどうですか?」とそのままゴールインします。
死者の記憶
非合法のイタコビジネス───死者のメモリを身体に挿入して一時的に死者の人格を復活させて遺族と再会させる商売───で、イタコをしていた男は、仲介人のないまま、老夫婦の願いを聞きいれ、わずかな金額でイタコを引きうけます。しかし、これがとんだ災難に。

メモリを挿入し、息子と再会した老夫婦は、「きっちり一時間で返す必要はないんじゃない」と返却を引き延ばします。それが「三人で食事に行かない」となり、やがて夜が更けホテルに宿泊しようとなり、一週間一ヶ月とずるずる時間が過ぎていきます。そしていつか身体を返却しなくてはと思いつつ、気がつけば十年の月日が流れているのでした。
結局その息子は、イタコの男の身体を借りたまま、結婚をして妻と子どもをもち、何十年も生き永らえます。そして、メモリを返さなかったことを後悔して死んでいきます。それで、もとのイタコ男のメモリがどうなったかというと───。
ありふれたアイデア
本来なら記憶と肉体は不可分のはずですが、人工の記憶装置のおかげでそれが別々となっています。記憶と肉体が切り離せるようになった途端、今まで予期しなかった問題がわらわらと生じてきます。その混乱具合がおもしろいです。

十分かそこらで長期記憶がうしなわれる世界も奇妙なら、他人の身体をとおして自分の記憶をながめるのもまた奇妙で、読んでいるとかなり変な感じがします。
いってしまえばこれは入れ替わりモノで、記憶の交換をつかって、「お前がオレで、俺がおまえで」をやっているのとおなじです。なので、決して目をひくようなアイデアではありません。むしろ、あるあるネタです。
定番ネタといってしまえばそれまでですが、『失われた過去と未来の犯罪』の秀逸さはそれだけではありません。この本は、記憶の考察が優れています。
ソフトとハード
『失われた過去と未来の犯罪』には、奇妙な読み応えがあります。
外部記憶装置の入れ替わりをきっかけに、あたかもおなじ人がふたり出来るような錯覚をみせるのは当然ながら、実は記憶の入れちがいを使って、人間の本質を問うているのではないか、どうもそんな気がしてなりません。
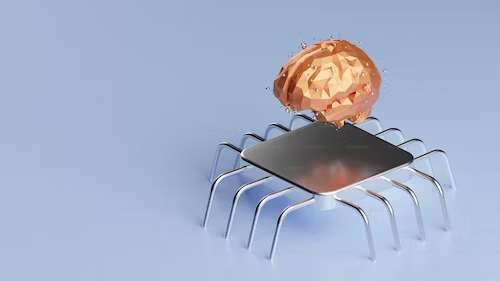
というのも、記憶が入れ替わることで、人間の本質が記憶にあるのか肉体にあるのか、そのことが曖昧になるからです。人格―身体―記憶は本来ひとつのものとして結合されていますが、仮に身体と記憶が分離した場合、どちらに人格をみるべきでしょう。
人格の基準───。
記憶と身体、どちらが人間を規定するのか。
ソフトとハードは、どちらがより本質的なのか。
そういった問題が、この物語には含まれています。
記憶の機能
そもそもこれを読むまで、記憶に人格がからんでくるとは思いませんでした。記憶は情報の貯蔵装置であり、単なるメモリーに過ぎません。脳がもつ重要な機能ではあるものの、貯蔵装置が、人格なり意識に直接影響するとはおもえません。
しかし、よくよく考えてみると、人間の規定の仕方にはいろいろあって、脳の機能をみても、判断、意思、思考、意識、感覚など、どれかひとつに特定することはできません。

そもそも記憶というのは人間が学習するために欠かせない機能で、おおむね三つの段階があるといわれます。
それは
①記憶の獲得段階、
②獲得したものを維持する保持段階、
③記憶を思い出す再生段階
です。

おもしろいのは記憶の獲得段階で、脳はそのまま記憶するのではなく、記憶するために、ある程度ものごとを符号化しておぼえています。そのままの形ではなく、取込みやすいかたちに外部情報を変えるのです。
そのうえで符号化した情報を貯蔵し、再生するときには、検索によって取りだします。つまり、記憶ひとつとっても、かなり高度な情報操作をしています。
その記憶に人格を見出すとすれば、記憶を、貯蔵装置とだけかんがえていては不十分です。
記憶の再生
獲得──保持──再生の一連の作業は、人の意思と深く関わっている。そんな気がしてなりません。
貯蔵だけでなく、再生までふくめた行為に、人格なり人の意思───正確には、意思を司るなにかがあるように思います。

仮に、ロボットが、記憶できるとしたらどうでしょう。ロボットがおこなうのは情報処理であり、0と1のやりとりでしかありません。そこには人間の意思も人格も存在しません。貯蔵としての記憶があるだけです。
しかし拙いながらも、ロボット記憶の獲得・保持・再生を行うとしたら、どうでしょう。我々はそこに人格───人としての印象を見るはずです。
そのため記憶は単一の機能としてはメモリーですが、獲得──貯蔵──再生が一連の行為としておこなわれたときは、人格とふかく関係してきます。そこには、なんらかの意思が存在します。
記憶と人格。「失われた過去と未来の犯罪」は、それを考えるいいきっかけとなりました。
記憶消去は殺人?
とくに興味をひいたのは、同じメモリーをコピーして挿入した双子の話です。
陽菜のメモリをコピーしてしまった双子は、どちらかメモリを返却する段となり、誤って挿入されてから今までの記憶が、自分の固有の体験であることに気づきます。
そして、こう訴えます。「この半年間、わたしはあなたとは違う人生を歩んできたわ。あなたは事の重大さがわかってないわ。わたしは過去半年間を失うだけじゃない。これから先の人生全てを失ってしまうのよ」

これは至極もっともな言い分です。誤ってコピーされたとはいえ、それ以降につくられた記憶はまぎれもなく本物なのですから。メモリを渡せば、現時点で陽菜と感じている自分のどちらかを永久に失うことになります。
半年間の記憶がなくなるということは、"半年の間の私"が消失することを意味し、"半年の間の私"をうしなえば、その先の未来をうしないます。したがって、たがだか半年にすぎないとはいえ、記憶をうしなうことはその人の死を意味します。
だとすれば、記憶は、人格を担保するもっとも重要なパーツではないか。そんな気がしてなりません。