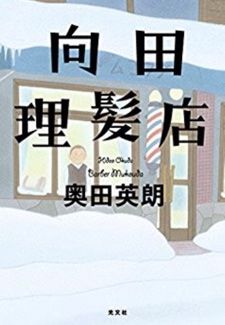
『向田理髪店』
奥田英朗
光文社
向田康彦は、北海道苫沢町にある昔ながらの床屋───向田理髪店の経営者です。
昭和四〇年代にはいり石油へエネルギー政策が転換されると、苫沢町では炭鉱の閉山が相次ぎ、人口流出が拡大、町の財政は破綻します。以降、衰退の一途をたどり、苫沢は高齢者の町となります。
高齢化を目の当りにし、床屋は自分の代までと、康彦は決めていました。しかし札幌で働いていた息子が、帰ってきたのをきっかけに、店の状況は変わります。康彦は会社でなにかあったのではないかと気を揉むのですが、そんな父親の気持ちも知らず、息子は、
"おれは地元をなんとかしたいわけさ。"
と地元愛を語りはじめます。

そして、
"このまま若者がいなくなったら、苫沢はどうなるのか。老人ばかりの集落になって、終いには滅んでしまう。それはマズイだろう。だから、自分は向田理髪店を継ぐことにした。"
と高らかに宣言。続けて、
"サラリーマンに代わりはいるけど、苫沢の散髪屋は代わりが効かない。このままだとあと十年ちょっとで苫沢の散髪屋はゼロだ。そうなったら、町民みんながこまるべさ。"
と力説します。さらに、
"従来通りの散髪屋でやって行こうとするから、先が見えねえわけだべさ。店を建て増ししてカフェを造るわけ。カフェを開いて、町民の憩いの場にしてもらって、新しい客を取り込むわけさ。"
と息巻く始末。

息子が将来設計を熱くかたる様を、康彦は冷ややかな目で見ていました。康彦にしてみれば、人口が減る一方のこの町で、理髪店に将来があるとは思えません。店に来るのは年寄りばかり。このままだと、じり貧になるのはみえています。
そうこうするうちに、康彦は息子がもどってきた本当の理由を知り、人知れず落胆するのでした。
花嫁問題
珠玉ぞろいの「向田理髪店」のなかにあって、特にオススメなのは「中国からの花嫁」です。四十才になる新郎が花嫁をもらう段となり、町民のあいだには祝福ムードが広がります。しかし肝心の嫁が中国の農村からきたことが知れるや、お祝いムードは一変、ためいきに変わります。

身近な人間の結婚はめでたいはずなのに、結婚相手が中国人と聞いたとたんに、手放しではよろこべなくなります。事実、康彦の胸中も複雑でした。過疎地の長男が結婚するのはそこまで大変なのか。息子の結婚をかんがえると、心配が先に立ちます。
花嫁問題はあっという間に広まり、おなじ町で暮らすにはお披露目が必要だとの機運が高まります。町の空気に押され、当初は乗り気でなかった新郎も渋々承諾、披露宴がおこなわれる運びになります。
しかし披露宴の当日、康彦は、会場に来て青ざめます。主役の新郎が会場からいなくなり、姿をくらましたのです。不測の事態に、関係者の間に緊張が走ります。康彦と青年団たちは、事実を伏せ、すぐさま新郎の捜索に乗りだします。
喜劇と救済

寂れた町のどこにでもありそうな光景が、奥田英朗が描くと、人生の一大事に変貌します。「中国からの花嫁」もそうですが、些細なことがここまで人を追い込むのか! と思わずにいられません。「ちょっと傷ついた人を的確に追いこむ」という意味では、実にいいところをついています。とはいえ、本人にとってはナイーブな問題であるものの、読んでる方は純粋に笑い話です。悲劇の加減だったり、てんやわんやする様がおもしろいです。
奥田英朗は本人にしかわかりえないナイーブな悩みをよく題材にしていて、その描き方には、ナイーブさを茶化す人の悪さがあり、それはそれでお茶目ですが、その一方でどこか悲劇から救おうとする優しさが感じられます。
悲劇は喜劇とよくいいますが、悲劇が喜劇に転じるのは、そこに救済があるからです。

たとえば向田理髪店に収録されている「赤い雪」では、
"気まずい雰囲気だけが残った。この件はしばらく遺恨になりそうである。もっともすぐに収まる。狭い世間だから、顔を合わせずにはいられない。となれば、誰かが間に入り、表面上は仲直りするのだ。この街はそうしてずっとやってきた。"
とあり、そこには田舎の処世術だったり、人生における開き直りが描かれています。こういったところに人生の救済を感じます。
くよくよしたってしょうがない。人間、結局、ひとりで悩み、ひとりで開きなおり、ひとりで悟るしかありません。
「向田理髪店」は、そういった開き直りのススメを、悩みと笑いを交えて説いているのだとおもいます。