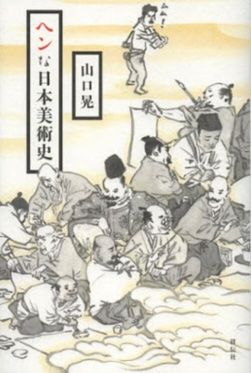
「ヘンな日本美術史」
山口晃
祥伝社
絵画や美術史のおもしろさより、山口晃の感性が勝ってしまう、そんな一冊です。
山口晃が感性を見せつけるのは、イラスト審査のエピソードを持ち出したときで、
”イラストレーション系の雑誌で審査した事がありまして、そこにはプロのイラストレーターを目指す方たちが投稿などをされています。そこに載っている絵と云うのが、こう申しては失礼ですが、わざとらしい個性、ニュアンスを出したようなものが多いのです。
「私らしく、伸び伸び描きました!」と云う雰囲気を出しつつ、その実まったく伸び伸び描いていない。”
と偏った現代の個性風潮を、一刀両断しています。個性重視のご時世に臆することなく、誤った価値観を、いとも簡単に斬って捨てるさまは痛快です。この人の感性───モノの見方は、並大抵ではありません。

山口晃はもともと皮肉っぽい人ではあるのですが、とはいえ、私らしく書きましたという書き方は全然私らしくないと、個性批判を正面から展開するあたり、なかなかひねくれていると思います。
でも、見方を変えれば、ひねくれているのは本人の性格ではないかもしれません。曲がっているのは周囲───世間のほうで、山口晃は案外、ありのままにもの申しているだけという可能性もあります。天才とバカは紙一重といいますが、正論と極論も紙一重なのです。
■鳥獣戯画は同人誌

読んでてなるほどと思ったのは、鳥獣戯画のくだりです。鳥獣戯画は平安末期から鎌倉時代にかかれた絵巻物で、兎やカエル、猿が、人間のように遊んでいる姿が描かれています。山口氏は、この鳥獣戯画に対して、
”複数の人が参加していって、結果として一つの作品とされる。後から描いた人は、同じ「鳥獣戯画」と呼ばれて一括りにされるとは恐らく考えていなかったでしょう。”
と述べています。この国宝絵画の特徴を、同人誌にたとえて評するなんて、大胆不敵もいいところです。さらに、
”あるいはお寺の人が「俺はこんな風にしてみた」とでも言いながら、仲間内で楽しみで見せ合っていたものが、いつの間にかちゃんとまとめられてしまったのかもしれない。”
といわれれば、なんだか、そんな気がしてきます。
同人誌感覚でつくったものが後世においてここまで広まるのですから、当世の人々の胸中もさぞ複雑でしょう。だったらもっと真面目に描いたのに。そんなぼやきが聞こえそうです。

鳥獣戯画の同人誌説は、なかなか興味深いものがあります。
たしかにあれを同人誌と考えると、鳥獣戯画の絵柄───技術も優美さもなくデフォルメされた感じさが、なんとなく理解できます。わざと下手にしているというか、下手を真似ているというか。あえて見る人にわかりやすく記号化しているのだとすれば、その志向はもはや同人誌の特徴そのままです。
そして鳥獣戯画を同人誌としてみるなら、あの絵巻物をひとつの作品として観るべきか、それとも作品群の総称と考えるべきなのか、そういった根本の定義が怪しくなってきます。事実、鳥獣戯画は作者不詳で、時代を超えて多くの人が参加していることから、誰の作品といえない代物になっています。ともすれば、鳥獣戯画は作品群の総称で、ひょっとしたらひとつのジャンル名ではないかと思えるのです。
■作家なるもの

鳥獣戯画に特定の作家ががおらず、様々な描き手が参加している事実をふまえると、日本の絵画というものは、案外、作者との結びつきが弱いことに気づきます。ゴッホといえば「ひまわり」が思いうかぶのに、日本人の画家で、絵画とセットになって記憶される人はほとんどいません。あえていうなら、葛飾北斎や写楽の浮世絵くらいでしょうか。
日本画、特に絵巻物になるとその傾向がつよく、あんなものにいちいち作者なんかつけてられないよといった趣が、どことなく漂っています。日本画が端正でいながら没個性の絵柄を志向するのは、作家が表に出ないことと無関係ではないでしょう。
■作家の個性とは?
は、鳥獣戯画や百鬼夜行が描かれた時代は、作家が軽視されていたのか。いえ、そうではありません。作家は作家でも、今と当時では、作家の考え方がちがうのです。

「ヘンな日本美術史」のなかで、山口晃は、
”このような作家性の在り方というのは、現代とは個人の枠の取り方が違ったことによるものでしょうが、それがこの四巻を見比べると感じられます。
今の作家性の在り方とは違いますが、それでは自分と云うものが無いのかと言えば逆で、描く事で「自分」が限りなく広がっているのです。”
といっています。まさにその通りです。この在り方は、先のイラストレーションの審査であった個性批判と通ずるものがあります。
作家性は、近代以前とそれ以降で考えがちがっていて、それはそのまま、個人という枠のちがいになっています。実は「作家」なるものは、近代画家によって生まれた概念で、個人には自由に物事をなし得る権利があると考えられています。
で、ひょっとしたら、山口晃は、この近代以降の作家について疑っている節があります。
作家をアーティストと解するなら、アーティストは大衆に受け入れられ、評価されて、そこではじめて才能がみとめられます。大衆に受け入れられることで、アーティストははじめてアーティストたりうるのです。いってみれば、その特別な才能を大衆に還元し、大勢の人を感動させ、おなじような共通体験をすることで、アートなり神秘性が生まれるのです。

近代以降にあらわれた作家が、個人の自由をベースにアイデアや感受性を発揮するアーティストだとするなら、山口晃が、世の中に氾濫する個性を皮肉るのも理解できます。
筆者が求める作家性やアートは、現代のそれとちがっていて、ここでいうアートはもうすこし下手で、味わい深く、みんなで楽しめるものとして語られているからです。特別な才能というより、おそらく絵心にちかいものです。
大衆に融けこんで育くまれる個性───アートには、いい加減からうまれる自由さだったり、下手からうまれる伸びやかさがあり、山口晃は、そこに重要性を訴えているのかもしれません。