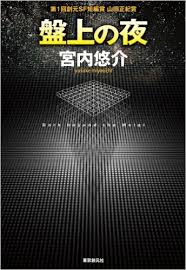
『盤上の夜』
宮内 悠介
東京創元社
失踪した女流囲碁棋士のお話しです。ジャーナリストの視点で語られるものの、記者がおもてに出ることはなく、直接ストーリーに関わることもありません。話の筋はあくまで稀有な能力をたずさえた女流棋士と、囲碁を打つ過程で彼女になにがおこっていたかが中心になっています。
囲碁棋士の灰原由宇を、ひとことで表すなら"異端"に尽きます。女性であることはもちろん、彼女は両手両足をうしなった異形の棋士として登場するのですから。
両手がないため、灰原には代わりに碁石を置いてくれる人が必要となり、それがたまたま同じプロ棋士の相田だったことから、囲碁をさしているのが灰原ではなく相田ではないかと物議を醸します。しかし周囲の雑音に反し、彼女は順調に勝星を重ね、女流棋戦を制覇、さらに女性本因坊へと登りつめます。

囲碁に関するかぎり、灰原はまさに天才でした。常人にはなしえない囲碁を打つ灰原は、その異形も手伝って、際立った存在感を放ちます。
灰原、語る
彼女のすごさを語るときに外せないのは独特の囲碁感覚で、それは通常の人間のものとまるでちがっていました。というか、ある意味で囲碁に純粋すぎたといえます。囲碁を刺すとき、彼女は人間の感覚とおなじように感じていて、
「星が痛い」
と自分の囲碁を表現しています。
灰原はその特殊な身体感覚により常人にはなし得ない囲碁を打ち、それはときに肉体を通じて盤とつながるほど直接的な感覚を有していました。肉体感覚をもって盤上でつながる特殊能力が、灰原の絶対的な強さであり、のちに最大の弱点となっていきます。

あるとき灰原は、忽然と、囲碁の世界から姿を消します。謎の失踪に、周囲は色めき立ちます。ジャーナリストは彼女の足あとを辿るうちに、介添人であり灰原の最大の理解者だった相田と接触し、相田から意外な証言を得ます。
それは彼女が語学の勉強をしていたというものでした。囲碁に語学? 一見なんの関係もない囲碁と語学が、どこでつながるのか。灰原は何を考え、どこに向かっていたのか。謎はさらに深まります。
驚くべきことに、彼女は語学を習得することで、盤上の感覚をよりクリアにしようとしていました。盤上でおこった感覚をすべて言語化する。それは誰も共有できない個人の領域であり、彼女がもっとも密接に関わる世界、囲碁という世界の言語化だったのです。

ひょっとしたら彼女は、盤上に現れるもうひとつの生命、星と星の命のやりとりを鷲掴みにしようとしたのかもしれません。盤上という戦場で、四肢のない彼女は躍動していました。肉体感覚を通じて盤とつながる彼女はまさに異端。いえ、ここまでいくと異常といえます。
灰原、失踪

ジャーナリストは、インタビューのとき、相田に灰原と関係があったのかと切り出します。相田はその事実を否定しますが、そのとき「盤上の性愛」なる言葉を語っていて、それがつよく印象に残っています。
体で交わるより、盤上で交わるほうが彼女との結びつきがつよい。
献身的に灰原をささえた相田もまた、盤上で狂った人間のひとりでした。あるいは相田は、灰原と囲碁を打つことで、灰原の肉体感覚に直に触れたのかもしれません。そして灰原が去ったあとに残されたのは、彼女と打った囲碁の思い出、圧倒的な虚無。押しよせる一抹の寂しさはまさに盤上の夜だったのです。
再び、灰原
さて、他方の灰原は、盤上の奥にひそむ感覚をさぐろうと彷徨い、その出口を言語に求めます。出口をもとめて駆け上がった灰原は、あまりに急激に駆け上がったがゆえに意識をとどめることができず、行方をくらましてしまいます。

盤上の感覚を求めてさまよった彼女の苦悩は、思考の奥にある暗闇に置き換えられるかもしれません。感覚の言語化。それは並大抵のことではありません。上も下も奥ゆきさえもない感覚の世界を、手さぐりで探しあてようとする行為は、無意味な作業のくり返しに似ています。
しかし、彼女はあえてその作業に没頭し、囲碁の感覚をクリアにしようとしました。そして異常なまでに研ぎすまされた囲碁感覚が、逆に彼女を苦しめます。盤上の感覚をもとめ、感覚に翻弄され、出口のない闇に飲みこまれて狂う。その様は、やはり異形というしかありません。
盤上と結びついた棋士の悲劇。儚くも悲しく、それでいて幸せなストーリーです。