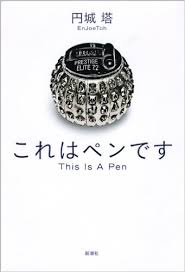
『これはペンです』
円城塔
新潮社
この本の価値は、出だしに集約されています。
叔父は文字だ。
文字どおり。
一見すると、なんのことかさっぱりわからない文章です。日本語として読めますが、意味を為しておらず、言葉遊びにしか見えません。そして、まるでわけのわからない奇妙な雰囲気は物語全般にただよっていて、いまからはじまるお話しを集約しています。そういう意味で、絶妙な出だしになっています。
夏目漱石の日本語
"これはペンです"というのは"This is a pen."という英語の教科書の最初にでてくるもっとも典型的な英文として読めるでしょう。これはなんのオマージュかと考えたとき、まっさきに思いあたるのは夏目漱石『吾輩は猫である』なのです。

吾輩は猫である。
名前はまだない。
これを英語にしてみると、
I am a cat.
I have a no name yet.
となります。
夏目漱石はあきらかに英語を下敷きにして日本語の再構築をおこなっていて、その証左の一端が「吾輩は猫」に表れています。夏目漱石が、新しい日本語をつかって小説を書くことができたのは、英語の文章を自在に扱えたことが、殊のほか大きいのです。そう考えるなら、日本の小説のルーツは、ある部分において英語の文法と密接に関わっているといえます。
もし円城塔がこのことを知っていて、"This is a pen."という英文を文字ってきたなら──それは、まさに文字どおり──かなり洒落てると思います。
叔父が文字である理由
ストーリーは、叔父と姪が手紙のやりとりしているという形式をとっていて、姪からみた物語が『これはペンです』となっています。
手紙をおくってくる叔父がどんな人かというととても変わっていて、天才であり変人、そしていささか変人の割合が優っているという訳ありな人物です。
叔父は、姪が生まれてすこしして海を渡ってしまったため、実際に会ったことはなく、一方で自ら開発した機械で文章を書くという論文を発表し、その研究分野で名を馳せたというのですから、もはや奇人です。聞くからに胡散臭い人物です。

姪は母親から、あれは変わっているからつきあってやってくれといわれ、叔父との手紙交流をつづけます。いまだあったことがなく手紙のなかでしか知りえない叔父は、手紙のなかの文字でしかない、というのが彼女の偽らざる実感でした。その叔父に対する実感が出だしの一文となって表れることになります。
叔父は文字だ。
文字どおり。
円城塔の奇妙な文章
円城塔はさほど読んでいないのですが、この人を読んでていつも思うのは、文字と文字のつらなりが奇妙にねじれるなあということです。円城塔特有の文字のつらなりは、うまいとか下手とかはべつにして、好きかきらいの問題に帰結するでしょう。あまり言いたくないのですが、いかにも純文学っぽいつらつらと上滑りする文章が綴られています。文章フェチには堪らないのではないかとおもいます。
円城塔は、小説の成立を理解していながら、それを確信犯的に外している節があり、小説にみえる文字のつながりをつくっておいて、敢えてむずかしそうな内容を語っているように見せています。しかし、むずかしそうなことを書いてるわりに、そこにあるのは小説らしき雰囲気だけで、実際にはなにもありません。というか、その文章は文意がとれないことが多々あります。

にもかかわらず、最低限、小説として読めてしまうから、この人の作品は不思議です。その原因はなにかというというと、やはり、さして意味のないねじれた文章にあると思います。小説はマンガや映画とことなり、ストーリーを展開していくうえで<文章>をつかうことになるのですが、事実だったり、思考だったり、感情だったりを文章で描きます。その文章をこねくりまわしておきながら、なにか大切なことを示しているようで、書き手の意思をまったく反映させない「らしい」文章をつむぐのが、円城塔の特徴です。
例えていうなら、そう、まるで自ら開発した機械で書いたみたいな文章なのです。
そう考えると、『これはペンです』は実験作 ではないかと思えてきます。小説のつくりかたを用いて、小説を装ったきわめて意味のない文字のつらなりではないかと。これはいかに小説らしく仕立てることができるかという実験をしているではないかと。人を食ったような無意味な試みではないかと。小説など無意味な文字のつらなりでしかなのだと。もし、そのことを意図的に突きつけているのだとしたら──
円城塔は、不気味なる御仁かもしれません。