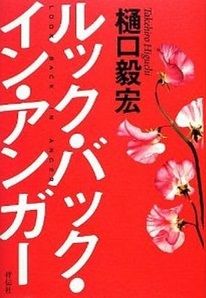
『ルック・バック・イン・アンガー』
樋口毅宏
祥伝社
エロ本出版社の悲喜こもごも。登場人物はいずれも歪んでいて、
ペニスに絶対の自信を持ち、愛する女を他の男に抱かせるという異常性欲の男。絶望の淵で酒をあおり精神と体をむしばむ男。不道徳の限りをつくす教祖めいた言動をとる上司。
となかなかの面子が、悪行の限りをつくします。狂った男たちを野に放ち、好き放題にさせ、不快感を撒きちす様は、読んでてドン引き。エグいです。

それでも作品のなかには、つき離すことのできないわずかな優しさがあるような気がします。同時に、忌むべき人間をつき離すことのできない葛藤はどこから来るのか、インモラルの果てに人間に残るものはなんだろう? と考えたとき、絶望の果てに希望がある──そんな陳腐な言葉を信じていいのかなと迷ってしまいます。
ううん。
どうかな。
女と酒と不道徳を突きつめてなにが生まれるのか?おそらくそこに意味はなくて、あるとすれば、ひとつは終らない宴のなかで、ひたすら踊りつづけた男たちがいることの証明であり、もうひとつは、悪行のかぎりを尽くした最低な男たちが、誰からも愛されなかったことの証明なんだと思います。なんというか。あまりにも虚無です。
樋口毅宏の品格
この本の主成分はエロと暴力の発散でなりたっていて、エロと暴力が協奏をかなで、ストーリーは破滅へむかって崩壊していきます。これだけフェチズムとエロに走り、官能小説めいた内容になりながら、お下劣にならないあたりは樋口毅宏の品格なのかなと思ったりします。ホントもうギリギリのバランスです。
下半身と暴力は似ていて、下半身も暴力も、吐き出したあとに一抹の悲しさしか残らないので、いうなれば、私たちが生きているのは、ちょっとずつなにかを吐き出すためかもしれません。吐き出し、崩れ、ちょっとずつなにかを失っていく。
その喪失は止めようがありません。樋口毅宏の根っこには、吐き出すことによって生じる悲しさが横たわっているのです。

樋口毅宏は他の人たちがためらってしまうようなところを飛び込んでいって、確信犯的にエンターテェイメントしてしまう傍若無人さがあり、その挑発的試みは、あたかも読み手を試しているかのようです。おもいきり読み手を選ぶものの、作者のフルスイングは読んでて気持ちがいいです。
だけど、最近なに読んだと聞かれたら、ルック・バック・イン・アンガーとは答えにくいですね。人格を疑われそうですから。