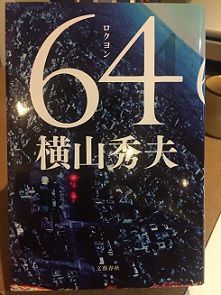
「64」
横山秀夫
文藝春秋
警察小説の代名詞ともいうべき横山秀夫。その横山が七年ぶりに書き上げた渾身作が「64」です。
捜査畑をあゆんできた三上は、広報担当となり、捜査の一線から退き、裏方へとまわります。おもな業務は新聞記者との対応です。就任以来、三上は粘りづよくマスコミ連中と対話をつづけ、記者たちとの信頼を築いてきました。
三上の胸には強い意志が灯っていました。それは広報室の改革です。三上は従来の態度をあらためるべく、広報室の改革に乗り出していたのです。 捜査情報を唯一絶対の武器とし、情報という鎧をまとって記者たちと対峙する。なれ合いの関係は避け、薄っぺらな警察批判や苦情は撥ねつける。毅然とした態度で、広報室と記者たちのあいだに「大人の関係」を敷いたのでした。

理想の改革へと邁進するなか、三上は、突如、記者たちへのチャンネルを閉ざします。自ら掲げた改革を一方的に破棄するです。無論、記者たちとの関係は悪化し、不満と不審が吹きだまった広報室は、一触即発の状態へと陥ります。
三上が豹変した理由はなんなのか?
きっかけは娘の家出でした。三上が愛娘の家出を告げ、その捜索を願いでると、上司にあたる警務部長は、本庁にファックスをながし、全国手配の手筈を整えました。警務部長は全国手配によって警察キャリアの威光を見せつけ、と同時に、自分の意に沿わない三上に対し恩を売ったのです。
以来、三上は警務部長の駒となり、自らの方針を変え、記者に情報を閉ざすようになったのです。
主人公

極上の警察小説──警察小説の到達点との呼び声が高い本作ですが、いささかやりすぎの感が否めません。娘がいなくなり、主人公の三上は愛娘を探すのですが、結局娘が見つからないまま話が終わります。探した娘が見つからない。 三上が娘が家出したという過去をひきずり、それが話がうごくきっかけになっているのですが、娘をさがすという流れが、途中から64の真相にとって代わられているのも気になります。
最初にあった過去=娘の欠如が知らぬまに脇へ追いやられ、にも拘わらず、終盤において夫婦のわだかまりが解消しているのが、ちぐはぐといえばちぐはぐです。
・娘の家出→探す→発見
・夫婦のわだかまり→解消
なら、わりとすっきりするのですが、
・探す→64の真相
・娘の家出→未発見
・夫婦のわだかまり→解消
となっているため、ストーリーと感情が噛みあいません。

また前半あれだけ悪役に徹していた警務部長が、後半にはいって完全に消えるのも不可解です。64絡みの事件が発生した時点で警務部長の存在はほとんど忘れられ、以降、まったく登場しなくなります。どうせなら最後の最後まで登場し、64の捜査を妨害して三上のまえに立ちはだかってもいいではないかと思ってしまいます。
ライバル
さらにいうなら、散々ライバルのように臭わせてきた二渡との対決がみられなかったことも、いささか合点がいきません。三上は64の真相にせまる過程で、影のようにうごく二渡を追うのですが、二渡と正面きって衝突する場面が見受けられません。なんだか煽るだけあおっといて、肩すかしを食らった感じがします。
このちぐはぐさは何なのかと考えたとき、その原因は、おそらく主人公がかかえる屈辱が多すぎることではないかと思いました。失踪した娘、マスコミとの対決、上司の警務部長との確執、64の捜査、醜悪な自らのルックス、妻との不仲など。
三上は自分の過去となるものをたくさん抱えていて、心にのしかかる描写はさすが横山秀夫の筆力でずしりと重く読み応え十分なのですが、重い個所がおおすぎるがゆえに、言い換えるなら主人公の過去が多すぎるがゆえに、どこかちぐはぐな印象となっています。

主人公が抱えていた悔恨はなんだったのか? それをどうやって乗り越えたのか、と問われれば、この「64」は主人公の過去がうまく絞りこまれていないのです。裏をかえせばそれだけ、書き手が主人公を造形するに際し、非常に格闘したことを物語っています。
七年もかかって書きあぐねた理由は、どうもこのあたりにあるのかなと思ったりします。
ワンテーマ。
ひとつに絞るというのは殊のほか大切です。