
社会を鋭く観察している本をピックアップした。年代もジャンルもバラバラ。でも読んでみるとひとつのテーマが浮かんでくる。われわれは個人であり個人としての思考をもつ存在だが、と同時に外部環境から影響をうける存在である。
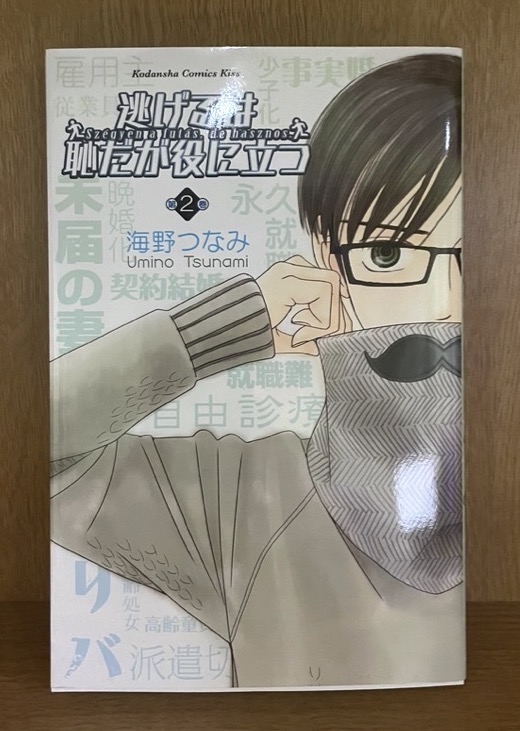
逃げるは恥だが役に立つ
海野つなみ
講談社
偽装結婚していた平匡とみくりが、自分たちの気持ちに気づき、契約と労働をのりこえて本物の夫婦になっていく。結婚生活から愛を差しひいたとき、はたしてそこになにが残るのか? という問いかけが、きわめて深い。
これは結婚というものを経済的活動の報酬と契約におきかえた思考実験なのだが、思考実験のわりにお金の部分が妙に生々しい。だが、それでいて本質をついているから笑うにわらえない。

無理
奥田英朗
文藝春秋
疲弊する地方都市を舞台にした犯罪小説。悪徳企業が純粋な従業員を食い物にするさまが、本当にありそうで怖い。地方特有の閉鎖性は、ややもすると抜けだせない蟻地獄にみえてくる。捕まったら最後、骨の髄までしゃぶりつくされる。
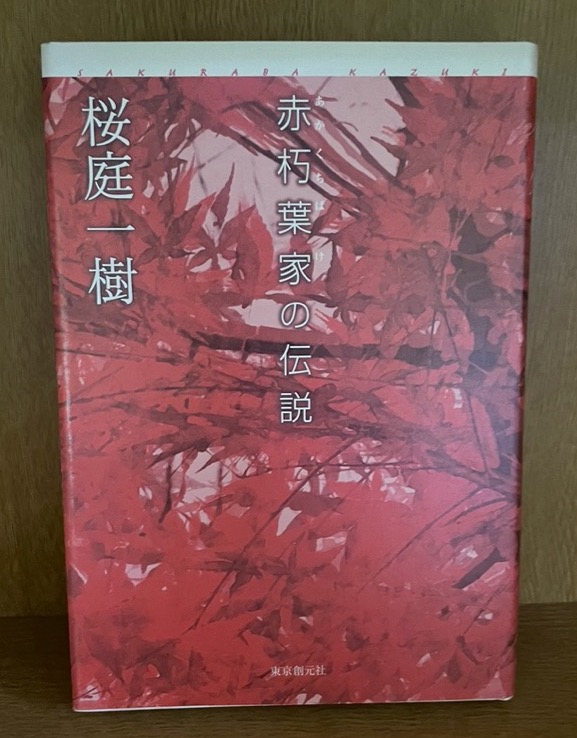
赤朽葉家の伝説
桜庭一樹
東京創元社
赤朽葉家にまつわる女性三代記。代がかわるごとに、世相がガラリと変わる。時代がかわれば社会が変わるし、社会がかわれば個人が変わる。この小説をよむと、世の中の価値観がこんなに変わったのかとびっくりする。
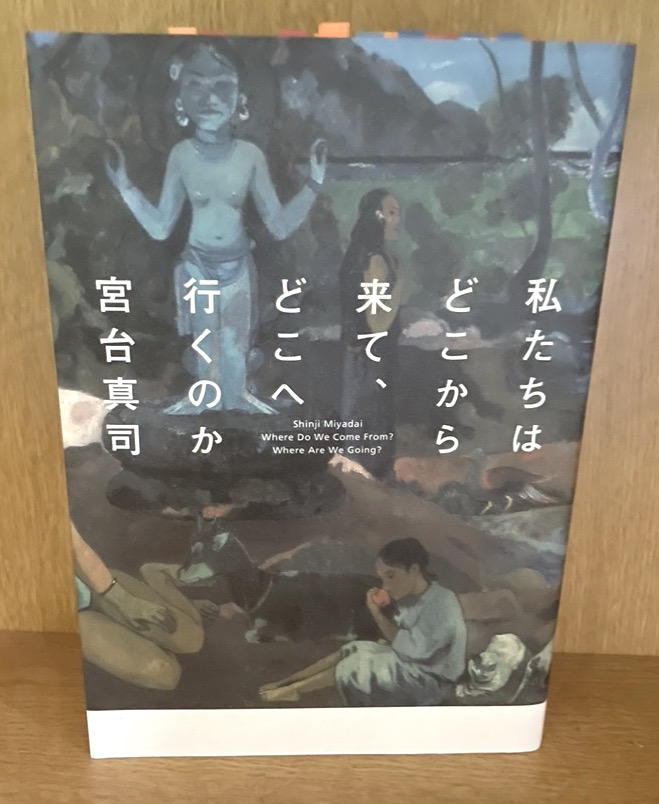
私たちはどこから来て、どこへ行くのか
宮台真司
幻冬舎
宮台真司は社会学者だが、ここで書かれているのは学者のそれではなく、ジャーナリストが語るような社会批評になっている。その姿勢/スタンスは、学者であることを放棄しているようにみえるし、あるいは放棄しているのは自分の立場ではなく日本の行く末かもしれない。その距離をおいた姿勢であるがゆえに、宮台は、課題を切りとるのに長けている。スパッと問題を指摘し、言いたいことをいう。
全体主義からポストモダンまで語れて、社会事件にも言及し、それでいてユーミンやサブカルも語れる学者などそうそういない。どこまでも宮台がかたるジャンルがどこまでも広がるのをみると、社会がヨコに広がるものだと、あらためてそのことに気づく。
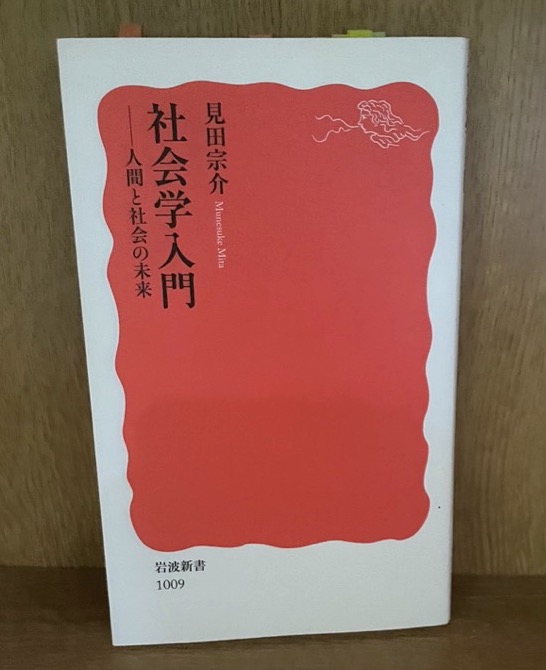
社会学入門
見田宗介
岩波新書
正統派の社会学者らしい発想で、モノを切りとっている。端的に短いことばで、現代社会の特徴を抽出しているのがすばらしい。宮台とは対照的に、社会がどのように発展するのか、タテ軸を意識してよむといっそうわかりやすい。またあえて個別の詳細なジャンルに分け入らず、抽象化にとどめているところも手際がいい。
全体をながめるには、森のなかに入らずぼんやりさせたほうがいい。そういう意味では、「社会学入門」は、宮台真司の問いに対するアンサーブック的な立ち位置にある。